FAQ
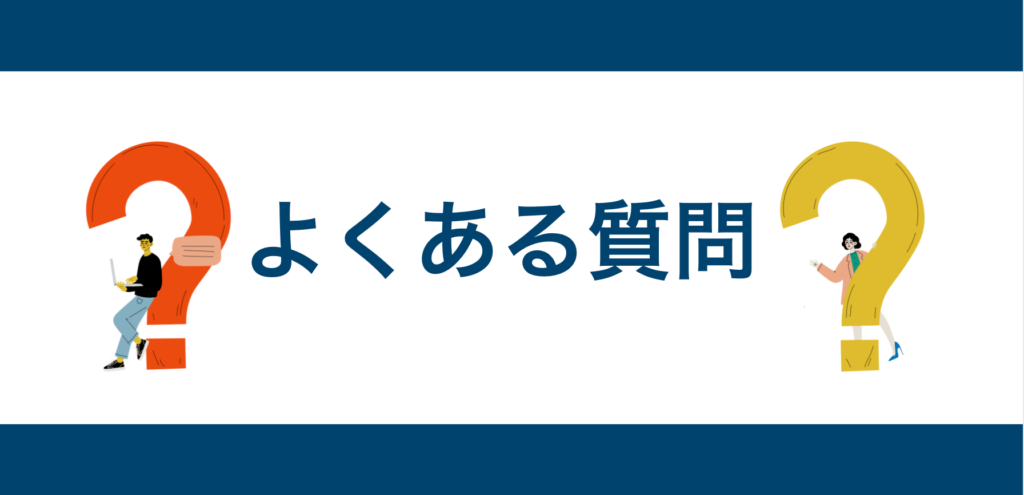
2024年11月14日更新
【ゼミの取り組みについて】
「Q. 2026年度のゼミのテーマが、アメリカと日本に軸足を置いたものとなってますが、日米以外の国や地域を扱う予定はあるのでしょうか?」
A. 森先生によると、アメリカが国際秩序をどう変えていくのかという大きな問題意識を整理するところから始まるので、欧州や中東などの地域・国々も研究対象になるということです。今年の春学期は、現3年生がチームに分かれて、アメリカの対ヨーロッパ政策、対中東政策、対アジア政策、通商政策、技術政策、国防政策についてそれぞれ調査し、ケーススタディとしてまとめ、夏合宿で発表しました。ですので、新4年生には、一定の知識のベースがあり、研究会での議論を通じて、テーマを発展させたり、深掘りすることができるのではないかと思います。」
「Q. 夏のゼミ合宿などの日程はどのように決めているのでしょうか?
A. 森先生の方針で、春学期の早い時点で、ゼミ生の都合を勘案し、全員の参加が可能な日時を探ります。先生が決め打ちで日程を決定することはありません。部活・サークルの試合や大会に対応しないといけないゼミ生は、例年の試合日程等をみれば、だいたいどの時期に重要な試合や大会などがあるか分かるので、それを把握したうえで全体の日程調整に臨みます。なお、平常のゼミの時間帯以外で実施されるゼミ活動は、夏合宿、合同ゼミ、OBOG会だけです。」
【入ゼミについて】
「Q. 森ゼミでは、現代の国際政治ばかりを取り上げているので表面的な理解しか得られず、歴史から現代をみる視点が欠けていると某ゼミで聞きましたが、森ゼミは歴史を扱わないというのは事実でしょうか?」
A. 今年の春学期には、アメリカ外交史のテキストを使って、トルーマン政権以降のアメリカ外交の歴史を学び、現代のアメリカ外交がいかに異質なものかという理解を深めました。また、国際政治経済学のテキストを使って、大英帝国から冷戦後のグローバル化に至る国際経済関係の発展の歴史も学び、経済関係の武器化や戦略産業のリショアリング、サプライチェーンの再編といった現代の経済分野の動きが、これまでの流れにいかに逆行するものであるかを学びました。
以上からお分かりいただける通り、森ゼミは歴史から現代をみる視点も重要視しています。
(また、もし今後も当ゼミに関する悪評を耳にすることがあれば、鵜吞みにせずに、まずは当ゼミまでお問い合わせいただければと思います!)
「Q. 森ゼミでは、どのような文献を使って研究会を実施しているのでしょうか?」
A. 歴史研究の文献から学ぶのみならず、理論研究の文献からも学びます。例えば、今年の春学期にアメリカ外交史のテキストを講読した際には、章と章の間に、同盟論、核抑止論、国際貿易制度、国際通貨制度といったテーマに関する理論研究の文献が挟まれたので、歴史と理論に学びました。昨年度は、例えばE・H・カーの『危機の20年』や、森先生の大学のゼミの先生だった髙坂正尭先生の『国際政治』といった古典的な名著も取り上げました。また、春学期は歴史と理論で基礎知識を身に付けましたが、秋学期は現代におけるリベラル国際秩序の変容に関するInternational Security誌というトップジャーナルの論文や、森先生の同門の先輩にあたる田所昌幸先生の『世界秩序』を講読するなど、なかなか大変ですが、知的な汗を掻きながら最先端の学術的な議論から学んでいます。つまり、歴史、理論、現代の研究と格闘し、多様なアプローチで国際政治に接近する手法を学んで、国際政治学の豊かさに触れています。」
Q.「入ゼミ課題や面接で特に重視することはありますか?」
A. 2024年度(昨年)の課題をもとに答えますと、入ゼミ課題の小論文(4,000字)では、指定された短いオンライン英文論考を3本読んで重要だと考えるポイントをまとめたのち(各300字)、自分で「問い」を立てて、それに答える(3,000-3,500字)というものでした。知識や情報の量よりも、物事を筋道立てて考えられるか、論旨が明快な文章を書けるかが一番の評価基準となります。興味深い「問い」を立てられると印象はさらに良くなると思います。「問い」は、どこかから借りてくるのではなくて、自分が率直に不思議だと思うことを問いにした方が良い小論文を書けると思います。面接では、知識を問う質問はしません。応募者の学問上の関心や人柄などに触れることが目的ですので、ご自身の事を素直に語ってもらえればそれで結構です。
Q. 「都合が合わずオープンゼミに参加ができないのですが、選考において不利になることはありますか?」
A. オープンゼミはあくまでも、森ゼミの雰囲気をみなさんに感じていただくということを目的としておりますので、当イベントの参加が入ゼミ課題や面接において不利になる、または有利になることは一切ございません。
Q.「書類と面接の重視する比率でどれぐらいですか?」
A. 書類選考と面接が同じくらい重視されます。
Q.「海外経験・英語力の有無は選考に影響しますか?」
A. 海外経験・英語力の有無は選考に影響いたしません。ゼミ課題と面接で総合的に判断いたします。
Q. 「倍率はどれくらいですか?」
A. 昨年は、応募者数が59名、選出者数が21名でした。よって倍率は約2.8倍です。
【毎回のゼミ活動について】
Q.「森聡研究会では、毎回の研究会をどのような形式で進めていく予定でしょうか?」
A. 毎週のゼミでは、国際政治の最新の動向に関する論文・論考を取り上げ(英語文献あり)、その内容について議論を重ねます。基本的に班ごとに発表等を行なっています。
春学期のゼミでは、その週を担当した班がはじめにレジュメとパワーポイントに基づいたプレゼンテーションを行い、その後、発表内容を各班が批判的に議論します。そして、発表を踏まえて自分たちで何を問うべきか検討し、翌週までの課題(問い)を自分たちで立て、1週間かけてじっくり考えてそれをまとめ、翌週のゼミで考えを持ち寄って議論してもらうという方式です。
並行して、チーム別に担当テーマについてケーススタディの調査を実施してもらい、調査結果をまとめ、夏合宿で発表してもらいます。(ゼミで講読する文献は、ケーススタディに関連するものとします。)
秋学期には、学期末に提出する短い共通課題のゼミペーパーを執筆する作業を通じて、文献調査、思考や論文の書き方などの基本的な作法を身に付けてもらいます。4年生になった際には、自分で自由に選ぶ現代国際政治に関するテーマについて、年度末までに研究論文を執筆しますので、あらゆるテーマに自由に取り組むことが出来ます。
年間行事としては、夏合宿、他大学との合同ゼミ、有志学生による海外自主調査旅行などを予定しています。合同ゼミでは、外交シミュレーションを実施して、日頃から鍛錬した力を実践・発揮する場も用意します。2024年6月には、九州大学のゼミと合同で次期トランプ政権のシナリオ予測対決を実施しました。ゼミは、来年度も火曜日4・5限に実施する予定です。
Q.「サークルやアルバイトが忙しいので、ゼミと両立できるか不安です。課題などは多いですか?」
A. 課題は主に①授業中にゼミ生同士で話し合って立てた問いや自分で立てた問いについて考えをまとめてくる(分量はA4 1枚程度。頻度は1-2週間に1回程度)、②文献発表(分量は本の1-2章、論文1本程度。頻度は学期に2回程度)です。
これまで担当してきたゼミの学生は、サークルとアルバイトの両方と両立できてきたようです。文献を読んで知識を吸収するための時間と労力と、物事をしっかり考えるための時間と労力をバランスよくとってもらい、社会人として必要な足腰の強さを鍛えてもらうための課題なので、自分が今そうした鍛錬にどれだけの時間と労力をかけるべきかを判断して、それと両立可能な形でサークルやアルバイトに取り組むという発想で考えてもらえればと、個人的には思います。
Q.「研究会では、英語の文献なども扱うのでしょうか?」
A. はい、扱います。日本語の文献は取り上げますが、それだけではなく、諸外国の文献で興味深い文献は、ゼミの中で取り上げて議論の材料にしていく予定です。ただし、最終的な入ゼミ生の人数にもよりますが、文献報告は4-5人の班で担当してもらいます。先述の通り分量は論文1本か本の1-2章程度です。膨大な英語文献を独りで抱え込むといったことにはなりませんので、英語力についても心配する必要はないと思います。
Q.「専門的な知識が無くても入ゼミは可能ですか?」
A. はい、大丈夫です。現役生も様々な参考文献に当たりながら、知識がない領域に挑戦してきました。
【その他ゼミ活動について】
Q.「研究会に入った後、海外留学に出ることは認められるのでしょうか?」
A. 海外留学を積極的に支援したいと考えています。単位を取得できるかどうかなど、事務的な事は各自で確認してもらう必要がありますが、研究会の担当教員としては、海外留学に出る学生さんを後押ししたいと思います。具体的な希望があれば、統一選考の面接のときに教えてください。
Q.「先生が法政大学でご担当されていたゼミのOBOGの皆さんと接点を持つような機会はあるのでしょうか?」
A. ゼミ生の皆さんの意向を確かめた上で、もし希望があれば、法政大学OBOGの皆さんと接点を持つ機会を設けたいと考えています。
法政でのゼミのOBOGは1期生から12期生までいます。10期生までは、すでに報道や金融からメーカーや官庁まで様々な業界に就職して活躍しています。毎年OBOG会を開催し、併せてOBOGによる就活相談会も開いて、OBOGが就職活動の相談に乗る機会も設けています。もし希望があれば、大学を横断した縦のつながりを持てる機会を設けていけたらと思います。
Q.「ゼミ活動以外でゼミ生はどんな交流をしていますか?」
A. ゼミ同期で旅行したり、テスト期間に集まって勉強したり、ゼミ後にご飯に行ったりしています!
